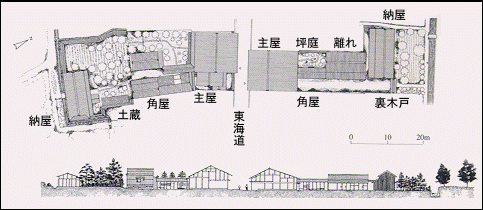人々の暮らし
公開日 2014年11月23日
更新日 2021年03月22日
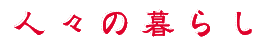
関宿の町屋のある敷地は、間口が狭く奥行の長い短冊状の敷地です。各家の主屋は、 街道に面して余地を残さず建てられ、主屋の背後には角屋(つのや)、 離れ、土蔵・納屋などが並んでいます。
関宿の町屋では、主屋の出入口は正面東側(下手)にとられ、居室が西側(上手) に並びます。出入口からは、主屋の奥まで続く通り土間が設けられるのが普通で、 通り土間の奥にはカマド・井戸などが設けられて炊事場(カッテ)になります。
主屋の間口規模は間口3〜4間程度が最も多く、間取は通り土間に沿って居室が一列 に並ぶ形式です。規模の大きな町屋は間口が6間前後になり、間取は通り土間に 沿って居室が二列に並ぶか、土間下手にシモミセを設ける間取になります。 これらが、関宿では最も一般的な間取形式であると言えます。
部屋は表からミセ・ナカノマ・オクノマ(ザシキ)と呼ばれますが、 四室になる場合はオクノマからブツマが独立して1部屋となります。 シモミセは家族の居室・帳場などとして使われ、旅籠屋に多く見られます。
ミセの上には「厨子(つし)」という低い二階があります。 旅籠などを除けば二階が座敷になることは少なく、物置として薪・柴などを蓄えておく場所でした。明治後期から大正以降の町屋では、二階が発達して座敷を設ける例が一般的になります。
関宿の町屋の間取形式
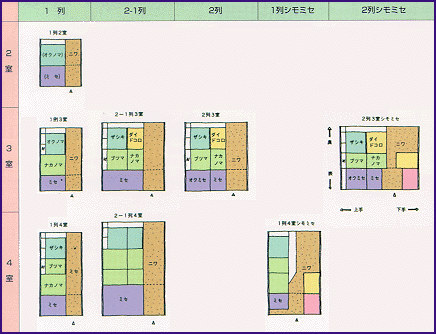
敷地の利用形態
マップをクリックすると、町屋の内部空間をご案内します。
お問い合わせ
市民文化部 文化課 まちなみ文化財グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-96-1218
FAX:0595-96-2414