未熟児養育医療について
公開日 2016年08月31日
更新日 2016年08月31日
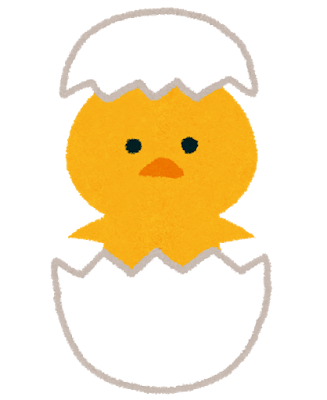 未熟児養育医療とは・・・
未熟児養育医療とは・・・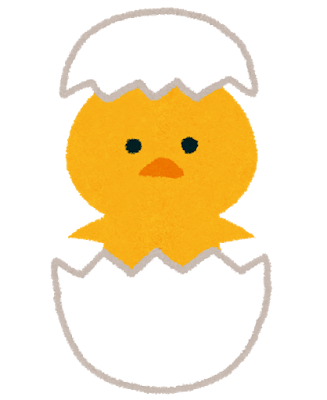
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担します。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。また、世帯の所得税額等に応じて、自己負担金が生じます。
なお、平成28年1月からの申請の際は、扶養義務者等のマイナンバーの提示が必要です。申請の際は、本人確認(扶養義務者等のマイナンバーの確認と身元の確認)を行いますので、「給付申請について」を確認のうえ、お越しください(※確認書類の記載事項が現状と異なる場合は、変更手続きを済ませてからお越しください)。
 対象となる方
対象となる方
次に該当するお子さんが対象となります。
1:満1歳未満(満1歳の誕生日の前々日まで)であること
2:お子さんの住所が亀山市内にあること
3:出生直後に(1)又は(2)の症状がみうけられ、医師が入院療育が必要と認めること
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがあるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便のないもの
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア)生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
 給付の内容
給付の内容
全国の指定養育医療機関で行う、未熟児の入院治療について医療の給付を行います。出生から継続している入院が対象となり、退院後の再入院や通院治療は対象外です。なお、給付の期間は、原則、医師が意見書に記載した診療予定期間となります。ただし、入院期間が満1歳の誕生日を超える場合は、満1歳の誕生日の前々日までが対象です。
 医療機関でのお支払い
医療機関でのお支払い
未熟児の入院治療における保険対象となる費用については市が負担しますので、窓口での支払いの必要はありません。ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口での支払いが必要です。
 自己負担金
自己負担金
書類申請から約2週間で世帯の所得税額などに応じた自己負担金の月額(徴収基準月額)を記載した養育医療給付決定通知書を送付します。自己負担金は、入院診療月の2、3カ月後に養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、市が定めた基準により算定し、通知しますので同封する納付書により納付してください。
入院された月ごとに、1カ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
なお、自己負担金の一部または全額については、子ども医療費の助成対象となります。
 給付申請について
給付申請について
原則として出生後2週間以内に、窓口に必要書類を提出してください。申請の承認には1週間ほどかかります。承認後、「養育医療券」、「養育医療給付決定通知書」を申請者に送付します。
なお、平成28年1月からの申請の際は、扶養義務者等のマイナンバーの提示が必要となりますので、下表を確認のうえ、ご持参ください。ご不明な点などは、担当室までお問い合わせください。
【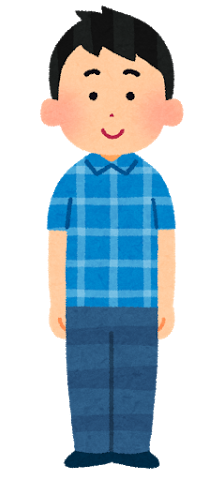 扶養義務者が申請する場合
扶養義務者が申請する場合 】
】
[1]扶養義務者等のマイナンバーの確認と[2]身元の確認が必要です。
|
個人番号カードを |
個人番号カードのみで[1]マイナンバーの確認と[2]身元の確認が可能です。 |
|
|
個人番号カードを |
[1]マイナンバーの確認 |
番号通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写しなど |
|
[2]身元の確認 |
運転免許証又はパスポートなど |
|
※身元確認書類についてはこちらをご参照ください→本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
【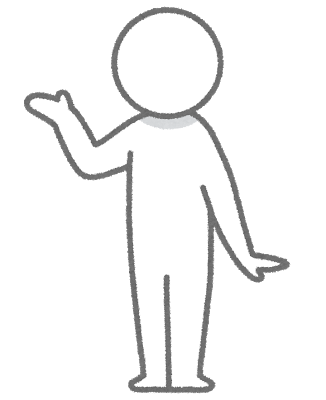 代理人の場合
代理人の場合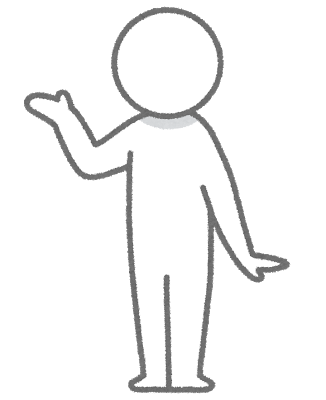 】
】
[1]申請者以外の方のマイナンバーが確認できるもの
[2]代理権が確認できるもの、または委任状(委任状[PDF:62KB]、委任状[DOCX:19KB])
[3]代理人の身元の確認ができるものが必要です。
|
[1]申請者以外の個人番号が確認できるもの |
申請者以外の個人番号カード又はその写し 申請者以外の番号通知カード又はその写し 申請者以外の個人番号が記載された住民票の写し等のいずれかをご持参ください。 |
|
|
[2]代理権が確認できるものまたは、委任状 |
法定代理人の場合 |
代理権が確認できるもの |
|
任意代理人の場合 |
上の委任状をご記入いただいた上で、ご持参ください。 |
|
|
[3]代理人の身元の確認ができるもの |
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど |
|
※身元確認書類については、こちらをご参照ください。→本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
◆法定代理人とは・・・法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
・親権者:申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方
・未成年後見人:申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方
・成年後見人:申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方
◆任意代理人とは
法定代理人以外は、すべて任意代理人となります。親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。
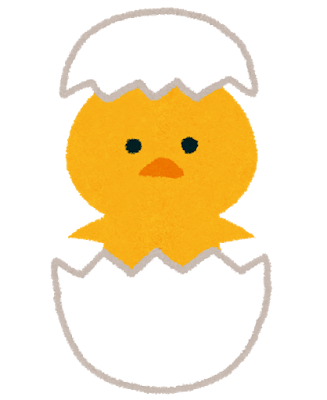 必要書類
必要書類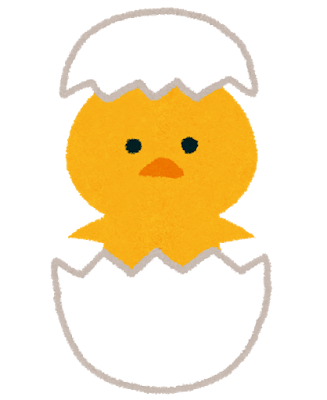
○養育医療意見書 養育医療意見書[PDF:82KB]、養育医療意見書[DOC:47KB]
※病院の担当医に記入してもらってください。
○養育医療給付申請書 養育医療給付申請書[PDF:70KB]、養育医療給付申請書[DOC:40KB]
※申請者(保護者)が記入してください。
○世帯調書 世帯調書[PDF:99KB]、世帯調書[DOC:43KB]
※申請者が記入してください。
○受療委任及び承諾書 受療委任及び承諾書[PDF:55KB]、受療委任及び承諾書[DOC:29KB]
※申請者が記入してください。
○申請者(扶養義務者)の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
○申請者(扶養義務者)の本人が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証等)
○印鑑(認め印)
○健康保険証(本人が加入する予定の保護者の健康保険証)
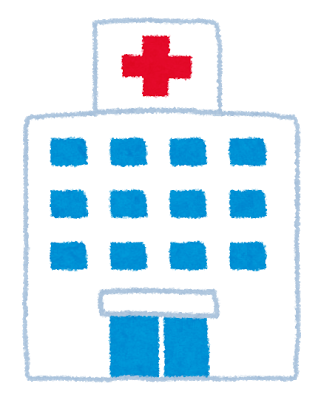 養育医療券
養育医療券
給付申請の承認後、申請者あてに郵送します。養育医療を受ける際に、医療機関の窓口で、健康保険証とあわせて養育医療券を必ず提示してください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード